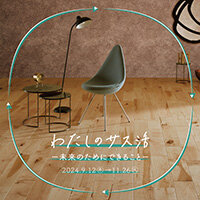産業廃棄物リサイクル処理プラントから出る瓦礫くずを、「東京の土着の素材」と見なして創作を続けるコンテンポラリー・デザイン・スタジオwe+。その最新作である照明器具「Remli」が、今秋OZONEにて展示されるこの機会にお話を伺い、その開発秘話や活動の背景から、彼らの創作の秘訣に迫ります。
現在の「産業のためのデザイン」が見落としてきているものにこそ、デザイン本来の目的が埋まっている-彼らがデザインに込めた想いを伺ううちに、「サステナブル」に対する彼らのユニークなスタンスも浮き彫りになってきました。

Photo: Hiroshi Iwasaki
Remli(2024)
東京近郊の産業廃棄物リサイクル処理プラントにおいて、再生利用可能な素材が選別・回収された後に残った細かい瓦礫くずを材料としてデザインされた照明器具。we+による研究プロジェクト「Urban Origin」と、ポータブル照明ブランド「Ambientec」との共同開発によって製品化・市販されている。
we+
リサーチと実験に立脚した手法で、新たな視点と価値をかたちにするコンテンポラリー・デザイン・スタジオ。林登志也と安藤北斗により2013年に設立。
利便性や合理性が求められる現代社会において、見落されがちな多様な価値観を大切にしながら、私たちを取り巻く自然や社会環境と親密な共存関係を築くオルタナティブなデザインの可能性を探究。デザイナー、エンジニア、リサーチャー、ライターといった多彩なバックグラウンドやスキルを持つメンバーが集い、日々の研究から生まれた自主プロジェクトを国内外で発表。そこから得られた知見を生かし、R&Dやインスタレーション等のコミッションワーク、ブランディング、プロダクト開発、空間デザイン、グラフィックデザインなど、さまざまな企業や組織のプロジェクトを手がけている。

林 登志也

林 登志也
はやしとしや
プロフィール
1980年富山県生まれ。一橋大学卒業。
学生時代より舞台演出に携わり、広告会社等を経て2013年we+ inc.を共同設立。リサーチを起点とする作品制作やインスタレーションといった領域横断型のアプローチから、ブランディングやコミュニケーション戦略まで、幅広い分野に精通し各種プロジェクトを手がける。国内外の広告賞、デザイン賞等受賞多数。法政大学デザイン工学部兼任講師(2019年〜)。その他、アワードの審査員、教育機関での講師、セミナー等での講演も行っている。

安藤 北斗

安藤 北斗
あんどうほくと
プロフィール
1982年山形県生まれ。武蔵野美術大学を経てCentral Saint Martins(ロンドン)卒業。
視点と価値の掘り起こしに興味を持ち、プロジェクトにおけるリサーチやコンセプト立案、空間〜立体〜平面のディレクションやデザインなど、複合領域的に手がける。2013年we+ inc.共同設立。国内外のデザイン賞を多数受賞。iF Design Award(ハノーバー)、D&AD Awards(ロンドン)審査員。武蔵野美術大学空間演出デザイン学科准教授、實踐大學インダストリアルデザイン学科客員教授(台北)、東北芸術工科大学デザイン工学部客員教授 等。
「リサーチと実験に立脚した手法」とは?
—we+のデザイン手法の特長として、「リサーチと実験に立脚した手法」が挙げられますが、具体的にどのような方法でしょうか?
安藤 私たちが2023年に手掛けたリサーチプロジェクトに、京都の丹後で営まれている絹織物の工程をリサーチし、その成果を展覧会「KYOTO ITO ITO Exploring Tango Threadsー理想の⽷を求めて」として発表したものがあります。昔の人たちは、自宅の屋根裏などで蚕を育て、その繭から生糸を作り、織物にして、それが破れたら別の物に仕立てて…糸も布も服も、ものすごく生活と密接に関係し合っていましたよね。ある種の「デザインの地産地消」です。でも、現在の私たちは、常に肌に直接「糸」が触れる状態で生活していても、その出自を気にすることはほとんどない。そこには効率性・経済性・利便性を優先して、「工場で作った物を量販店で買う」ことが常態化してしまった、今の私たちの生活の姿があります。

リサーチプロジェクト「KYOTO ITO ITO」(2023)
we+とNUNO、大垣書店によって立ち上げられたリサーチプロジェクト。京都・丹後エリアの養蚕・製糸・製織という絹織物ができるまでの各工程をwe+がフィールドリサーチし、その成果を展覧会「KYOTO ITO ITO Exploring Tango Threadsー理想の⽷を求めて」として発表したもの。
安藤 私たちが「リサーチ」を重視するのは、デザインが向き合うべき「物の本質」に気づくためと言えるかもしれません。この糸はどこから来て、誰が、どのように作り、布になったのか…私たちも、糸の生産現場に出向き、フィールドリサーチをするまで、そのディテールやリアルな実感は知りませんでした。どんなデザインを手掛けるにしても、素材が持つ表層的な情報は知っていても、本質的な情報にはリーチできていない。だからこそ足を使ってリサーチすることを重視しています。
林
便利さを享受する良い面もありますが、それにしても加速が速すぎやしないか?という疑問があります。長い年月をかけて培ってきた人間と物とのバランスや文化が、急速に失われている。私たちはデザインを行う上で、そうした部分に目を向けていきたいということです。あとは、素材の成り立ち方を知った上でものを作ることが、感覚的にとても楽しいです。
扱い方や付き合い方を分かった上でものを作る喜びは、なるべくいろいろな人に知ってもらいたい。「KYOTO ITO ITO」のアウトプットが「展覧会」であったように、リサーチの成果を展示会や本、写真や動画によるウェブでのレポートのような形でも発表しているのには、そうした思いも込めています。
—そうした広いデザインの概念の中で、「サステナビリティ」という視点は、どのように位置づけられるのでしょうか?
林 デザイナーとしてサステナビリティをどう考えるかに関しても、自分たちなりに調べたり、フィールドワークしたり、手を動かしたりすると、社会的に大問題と言われていることが、実はそんなに大したことではなく、本当は別のところに大きな問題や原因があることに気づく…というようなことはよくあります。例えば、廃棄物問題では、とにかくゴミを減らせと言われますが、廃棄物処理場やリサイクル施設では、すごい精度で分別作業をしていて、可能な物はほとんどリサイクルできる仕組みが構築されています。それでも最後まで残ったものは、埋め立てるしかないとなるのですが、「そもそも分別できるもの作りをしていない」ことこそ問題の本質だと、つまり「デザインの責任」に気づくのです。
あるいは、分別して再利用できる状態にしても、受け入れる処理施設や仕組みがないために、遠距離の場合によると海外に送るしかなかったりすることも。「その費用や輸送時に排出するCO2はどうなのか?」「結局は日本で埋め立てたほうが環境に優しいのではないか?」…というように本末転倒なことが見えてくることもあります。だから私たちは、リサーチをしっかり行って、自分たちなりの理解とアウトプットで知り得たことをきちんと伝えることを心掛けていますし、そこまでが「デザイナー」の仕事だと思っています。

we+のリサーチプロジェクト「Urban Origin」の根幹を成す作業。産業廃棄物リサイクル処理プラントで、分別し尽くされた後に残る「廃棄物の中の廃棄物」の中から、創作の種となる、「東京の土着の素材」を回収していく。